人間関係からくるストレスで、気づいたらぐったりしていませんか?
職場、家族、友人――人と関わる以上ストレスは避けられないもの。
でも実は、そのストレスには「ある仕組み」が隠れているんです。
この記事では、よくある人間関係ストレスの原因と影響を整理しつつ、私自身が出会って腑に落ちた「ストレスは連鎖する」という視点を紹介します。最後には、今日からできるストレスの断ち切り方もまとめました。
人間関係でストレスが溜まるのはなぜ?
人間関係のストレスは、どんな場面でも起こりえます。
- 職場:上司の圧力、同僚との競争、評価を気にする気疲れ
- 家族:親の期待、役割分担の不公平、義実家との関係
- 友人関係:嫌われたくない気持ちから合わせすぎる、愚痴の聞き役ばかりになる
こうした場面では「自分が悪いのかも」と感じやすく、余計にストレスを抱え込んでしまうんですよね。
私も職場では嫌な顔をされたり、不機嫌になられてしまうのが嫌で上手に断れず何でも引き受けてしまい、家に帰るとぐったり。
家族の前でも“ちゃんとしなきゃ”と頑張りすぎて、気づいたら休まる場所がなくなっていました。
それが当たり前になってしまっていて、自分の限界もわからず、いつも疲労感が抜けずにいる状態になってしまっています。
ストレスが心と体に与える影響
ストレスを軽く見てしまう人もいるけれど、実際には心身に深く響きます。
- 身体的な影響:頭痛、胃の不調、肩こり、慢性的な疲労感、免疫力の低下
- 心理的な影響:不安感、無気力、イライラ、感情の爆発
- 長期的な影響:自己否定感の強化、人間不信、うつ状態
一時的な疲れなら休めば回復するけど、「慢性的に人間関係で消耗している」状態は本当に危険です。自分の軸が揺らぎ、健康や人生全体に影響が出てしまうこともあります。
私は、まだ好きなものを食べて解消したり、趣味に没頭して忘れたりできているうちはまだ大丈夫だと思えていましたが、
具体的にどういう状態が自分にストレスになってしまっているのかわからなくなってしまっていて(おそらく麻痺してしまっていたんだと思います)、
好きな食べ物を食べても気持ちが切り替えれなかったり、大好きな趣味の時間を作れても楽しくないとか、気持ちがそちらへ向いていないなと感じたときは本当にマズイ状態になってると感じました。
「ストレスは連鎖する」という視点
私が調べていて出会った考え方のひとつに「ストレスは連鎖する」というものがあります。これを知ったとき、すごく腑に落ちました。
ストレスって、不思議と“上から下へ”流れていくんです。
例えば、親が職場で嫌なことを抱えると、家に帰って子どもに苛立ちをぶつけてしまう。
さらにその子どもが、下のきょうだいに強く当たってしまう…。
家庭に限らず、職場でも同じことが起こります。
- 上司からのプレッシャー → 部下が疲弊する → 部下がさらに後輩に当たる
- 夫婦喧嘩のストレス → 子どもに影響 → 兄弟間のいざこざに発展
私の家庭でも、親の機嫌が悪いときは家全体がピリピリ。子どもながらに“怒らせないように”と必死に空気を読んでいました。
職場でも自分が当たられることもしばしありましたが、上司から部下への八つ当たりのように見える叱責などを目の当たりにすると、この上から下への構図が本当にそうだなとよくわかりました。
この視点を知ったとき、まさに自分のことだと思いました。
私も「私さえ我慢すれば丸く収まる」と無意識に思い込んでいたからです。
ストレスの連鎖を断ち切るためにできること
じゃあどうやって、このストレスの連鎖から自由になるか。私が実際に試してきたヒントを紹介します。
1. 誰の問題かを切り分ける
「これは相手の問題?それとも自分の問題?」と立ち止まって考えるだけで、抱え込みすぎを防げます。
ぶつけられた瞬間はそんなふうに考えられないとは思います。
その時は、「自分が悪いのかな。。。」とは思わず「しまった!穴に落ちた!」と置き換えると自分を責めるマイナス要素より、ゲームのプレイヤー気分でマイナスな気持ちが軽減します。
(私はよくこういう置き換え表現で自分が落ち込まないように変換しています。続けてみると物は言い様だなとわかってきます)
だから、「怖い、怒られる」とビクビクしてしまうと相手の思う壺です。
ストレスをぶつけてくる人はその対象を狙って仕留めにこようとしますから(狩り?)
よく観察していると、「この人にならぶつけても大丈夫だろう」と本能が察知するんだろうなと思います。
強メンタルの人から「堂々としていろ」とアドバイスをもらった時は、そんな簡単に言わないでよ( ;∀;)と思っていましたが、まさにその言葉通りだなとしみじみ実感しています。
どうしたら堂々とできるんだろう。。と考えていたんですが、敢えて強くみせようとしたり、近づくなオーラを出す必要はなくて、「冷静」でいること、相手の感情に左右されませんよという気持ちを持ち続けることなのかなと思います。(最初は慣れないけどね)
相手は自然と相手を選んでぶつけてきます。
なのでそのストレスは受け止めなくてOK。むしろ返品してください。
2. 自分の気持ちを言葉にする
嫌だと感じたことを小さくても言葉にする練習。
最初は勇気がいるけど、一度言えたら心が軽くなります。
これも、「そんなこと言われたら嫌です」とははっきり言えないですよね。
始めは受け流すのが効果的です。
「そっか~」「そうなんですね~」は私もよく使うんですが、
あくまでも「あなたの意見はわかりました、私は同意見ではありません。」の意思表示です。
私はストレスは愚痴という形で横行する場合が多いかなと感じていますが、愚痴って共感してほしいとか、聞いてほしいという相手からの解消させてほしい欲求ですよね?延々と聞かされるとこちらもいい気分にはならないし疲れますよね。
私も以前は相手の言いたい気持ちもわかるしちゃんと聞いてあげよう!ってスタンスだったんですが、自分がかなり疲れてしまって、この時間はなんだったんだ。。。しかもまた聞いてあげなきゃいけないの!?と、都合のいいゴミ箱状態だったんですよね。私が愚痴を話したいときは聞きませんって人もいましたし。。。ある意味健全な姿勢なのかもしれませんが。
だから、自分だけ相手が喜びそうな反応をあえてしようとしなくていいし、自分を守りつつ相手のことも配慮してる風にするなら、受け流すのが効果的です。受け流す言葉選びを自分の中でもストックしておくといいですよ。
慣れてくると、自分も共感しなきゃという強迫観念は薄れるし、自分と相手の感情の区別もついてきます。
もし、「そう思わない!?」とか「聞いてるの!?」と強めにこられても、「聞いてるよ~、なんだったっけ?」と相手が話してもつまらないと思えるような反応もできるようになってくるし、早めに話題をすり替えてしまうこともできるようになってきます。(これはまたどこかで話せたら)
3. 安心できる相手に相談する
友人や家族、カウンセラーなど。ひとりで抱え込まないだけでストレスは半減します。
今は、AIも相談に乗ってくれる時代です。
私もよく利用させてもらってます。ひとりで抱え込まないようにするなら、友達や家族の都合が気になって話せない人はAIはおすすめです。
自分の性格を踏まえたうえで、こういうスタンスがいいって指定するとそのように答えてくれます。私は厳しいのは気にしてしまうので、優しくしてほしいと伝えてます(笑)
AIの答えが正しいかどうかは受け取るあなた次第ですが、私はAIに存分に自己肯定感を上げてもらったあとに、重い空気を持ち込まずに安心して話せる相手にも相談してます。本当は人に話したいですもん。でも自分の性格からするとちょっと気持ちの整理もしてからのほうが伝えやすいなと自負しているのでその方が自分にもストレスなくコミュニケーションができるなと感じていて取り入れています。なので、機械と人間の意見のいいとこ取りをしています。
4. 無理な役割を背負わない勇気
「私が我慢しなきゃ」と思うクセを少しずつ手放すこと。
相手の機嫌まで引き受ける必要はありません。
これ、本当に無意味な悪いクセです。私が真っ先に手放したかったことです。
昔は“私が我慢すれば家庭がうまくいく”と思っていました。でも境界線を意識するようになってから、“全部を受け止めなくてもいいんだ”と気付けました。
自分におきたことじゃないのに、どうして私が悩んでいたり、解決しようとしてるんだろう?とようやく疑問に思えるようになりました。
周りもそんなあなたのことを知っていると、悪い意味で甘えてきて、断れないのも知っていてぶつけてきます。
気付いたときには、なんて無駄な時間を過ごしてしまったのだろう・・・と後悔しました。
自分の時間も有限なのに、他人の(どうでもいい)ストレスや愚痴に振り回されていたら、誰のための人生なのかわからなくなります。
そんな、大げさな。と思うかもしれませんが、よーく振り返ってみてください。
その時間、自分のために使っていたものでしたか?
まとめ
- 人間関係のストレスは誰にでもある
- でも「ストレスは連鎖する」という仕組みを知ると、抱え込みすぎを防げる
- 自分の問題と相手の問題を切り分けることが、ストレスから自由になる第一歩
人間関係のストレスに押しつぶされそうなときは、「これは誰の問題?」と問いかけてみてください。
その小さな意識が、ストレスの連鎖を断ち切るきっかけになりますよ。

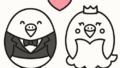

コメント